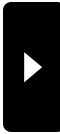2023年01月21日22:11
大河ドラマ「どうする家康」をより深く理解するために、というか自分が理解するために、磐田市内にある家康と関わりがあると言われている場所を紹介していきたいと思います。
まずは自宅のそばにある「天竜川の渡船場跡」から。
元亀3年(1572年)、徳川家康は一言坂の戦いで破れ、数人の家来を連れて現在の磐田市池田の地まで逃げて来たが、土地の人は戦場になることを恐れ、みんな逃げ去ってしまい、一人も居ませんでした。
家康はあちらこちらさがし回って竹薮の中にかくれていた元紀州の浪人藪の内善右衛門を見つけて、是非天竜川を渡してくれと頼みました。
渡船方の庄屋をしていた善右衛門は気の毒に思い、船頭衆を10人程呼び集め、西岸の半場まで無事に渡すと、家康が「ここは何と申すか」と聞いたので、「半場と申します」と答えたところ「これから半場の姓を名乗れ」といわれたということです。
また家康を西岸に渡してから、武田軍が追撃しては気の毒だということで舟を熊野の長藤で有名な行興寺の西の池に沈め、櫓を天白神社境内にあった池にかくし、後にそれぞれ「舟かくしの池」、「櫓かくしの池」というようになりました。
このような事から、家康を助けた恩賞として天竜川渡船の特権(専用許可状)を与えられたといわれ、半場家が代々天竜川の渡航権を独占していたそうです。
ちなみに私の同級生にも、ご近所さんにも半場さんがいらっしゃいます。
写真は、その渡船場の跡地を表す石碑です。

ツッコミどころはたくさんありますが、内容は、豊田町誌を参照にしました。
#どうする家康
#天竜川
#渡航権
#半場の姓
#家康はたくさんの人に助けられている
磐田でどうした家康 001≫
カテゴリー
大河ドラマ「どうする家康」をより深く理解するために、というか自分が理解するために、磐田市内にある家康と関わりがあると言われている場所を紹介していきたいと思います。
まずは自宅のそばにある「天竜川の渡船場跡」から。
元亀3年(1572年)、徳川家康は一言坂の戦いで破れ、数人の家来を連れて現在の磐田市池田の地まで逃げて来たが、土地の人は戦場になることを恐れ、みんな逃げ去ってしまい、一人も居ませんでした。
家康はあちらこちらさがし回って竹薮の中にかくれていた元紀州の浪人藪の内善右衛門を見つけて、是非天竜川を渡してくれと頼みました。
渡船方の庄屋をしていた善右衛門は気の毒に思い、船頭衆を10人程呼び集め、西岸の半場まで無事に渡すと、家康が「ここは何と申すか」と聞いたので、「半場と申します」と答えたところ「これから半場の姓を名乗れ」といわれたということです。
また家康を西岸に渡してから、武田軍が追撃しては気の毒だということで舟を熊野の長藤で有名な行興寺の西の池に沈め、櫓を天白神社境内にあった池にかくし、後にそれぞれ「舟かくしの池」、「櫓かくしの池」というようになりました。
このような事から、家康を助けた恩賞として天竜川渡船の特権(専用許可状)を与えられたといわれ、半場家が代々天竜川の渡航権を独占していたそうです。
ちなみに私の同級生にも、ご近所さんにも半場さんがいらっしゃいます。
写真は、その渡船場の跡地を表す石碑です。

ツッコミどころはたくさんありますが、内容は、豊田町誌を参照にしました。
#どうする家康
#天竜川
#渡航権
#半場の姓
#家康はたくさんの人に助けられている