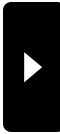2022年10月06日18:39

昔から天竜川の下流は、磐田原台地と三方原台地の間は洪水時にはあり余る大水に、また日頃は逆に水不足に悩まされていました。
戦国時代、徳川家康は、伊奈備前守忠次に新田開発を命じ、現在の磐田市加茂・匂坂付近で代官を務めていた平野重定が大井堀の開削にあたりました。
開削にあたったと言っても、ひとりで事業を成し遂げたのではありません。今でいう公共事業ですね。
重定は、寺谷の天竜川支流に取入口を設け、南部の浜部地区までの12キロに大井堀を掘り、導水したのです。
これにより73カ村2万石余りの新田が灌漑され、この地域にとって重要な用水となりました。
その後も用水路は延長され、現在も寺谷用水と呼ばれており、旧村名「井通村」の由来にもなりました。
その寺谷用水が本日「世界かんがい施設遺産」に登録されました。

磐田市加茂の用水近くにある大円寺には、重定のお墓があります。

また埼玉県伊奈町のマンホールカードは、伊奈備前守忠次がデザインされています。

#天竜川
#寺谷用水
#徳川家康
#どうする家康
#平野重定
#大円寺
#公共工事
#伊奈備前守忠次
#マンホールカード
寺谷用水が世界かんがい施設遺産に登録≫
カテゴリー

昔から天竜川の下流は、磐田原台地と三方原台地の間は洪水時にはあり余る大水に、また日頃は逆に水不足に悩まされていました。
戦国時代、徳川家康は、伊奈備前守忠次に新田開発を命じ、現在の磐田市加茂・匂坂付近で代官を務めていた平野重定が大井堀の開削にあたりました。
開削にあたったと言っても、ひとりで事業を成し遂げたのではありません。今でいう公共事業ですね。
重定は、寺谷の天竜川支流に取入口を設け、南部の浜部地区までの12キロに大井堀を掘り、導水したのです。
これにより73カ村2万石余りの新田が灌漑され、この地域にとって重要な用水となりました。
その後も用水路は延長され、現在も寺谷用水と呼ばれており、旧村名「井通村」の由来にもなりました。
その寺谷用水が本日「世界かんがい施設遺産」に登録されました。

磐田市加茂の用水近くにある大円寺には、重定のお墓があります。

また埼玉県伊奈町のマンホールカードは、伊奈備前守忠次がデザインされています。

#天竜川
#寺谷用水
#徳川家康
#どうする家康
#平野重定
#大円寺
#公共工事
#伊奈備前守忠次
#マンホールカード